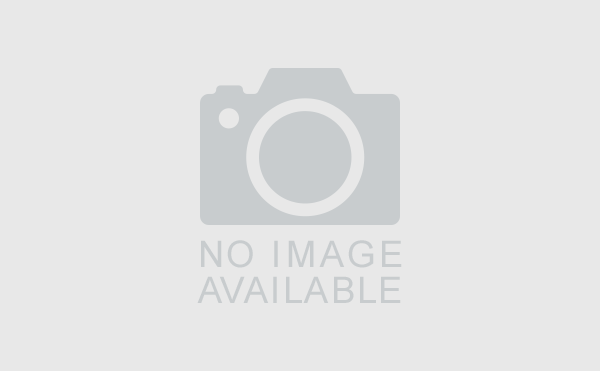CISPRって、そもそもナニ?

はじめに
今回は「CISPR(シスプル)」という言葉について分かりやすく解説していきます。「え、それ何?おいしいの?」と思った方もいるかもしれませんが、残念ながら食べ物ではありません。でも、私たちの生活には実はとっても大切なものなんです。
CISPRとは?
CISPRとは、「国際無線障害特別委員会」という、なんだか堅そうな名前の組織のことです。この委員会は、電磁波や電波の「〇〇障害」を防ぐために存在しています。具体的には、電気製品などから出る「妨害電波」を減らす方法やルールを決める仕事をしています。
- CISPRはフランス語で”Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques”の略。英語だと「Special International Committee on Radio Interference」という名前になります。
- この組織は意外に古く1934年に設立されました。世界中の電波環境を守るために、国際的に規格や基準を統一することを目的に活動しています。
なぜCISPRが必要?
日常生活では、テレビやラジオ、Wi-Fi、スマートフォンなど、いろんなデバイスが電波を使っています。ですが、これらが同時に動いていると、お互いの電波が「ぶつかり合って」混乱が起きる可能性があります。例えば…
- スマホを置いたらラジオが「ザーザー」と雑音だらけになった。
- 電子レンジを使っているとWi-Fiが遅くなる。
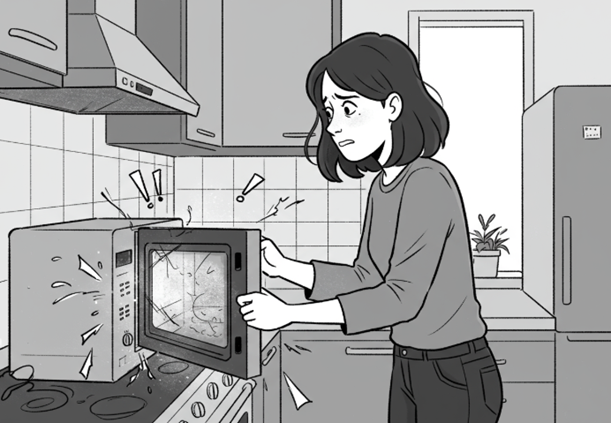
これらは、電化製品から出る「妨害電波(電磁波)」が原因の一例です。この妨害電波が無秩序に増え続けると、通信機器がうまく動かなくなったり、重要な機器が誤作動を起こしたりする可能性があります。これを防ぐために、「どこまでの電磁波ならOK」「どのくらいがダメ」という基準を決める必要がある。それがCISPRの役目なんです。
どんなことをしているの?
CISPRは大きく分けて、以下のような仕事をしています。
- 妨害電波の測り方を決める
たとえば、「この製品から出る電磁波の強さをどうやって測るか?」という方法を統一しています。測る道具や手順が違うと正確な比較ができませんよね。 - 妨害電波の許容値を決める
「この機器からこれ以上の電磁波が出るのはダメ」というルールを作ります。これを守ることで、機器同士が互いに悪影響を与えないようにしています。 - 機器を種類ごとに分類
世の中にはいろいろな電化製品がありますよね。CISPRでは、用途や分野ごとにグループを作り、それぞれの基準を定めています。以下はその一例です:- 医療機器や工業用機械の電磁波を管理
- 家庭用電化製品(冷蔵庫、掃除機など)
- 車や電車などの機械設備
- コンピュータ、スマホなどの情報通信機器
CISPR規格って?
みなさんが普段使っている電化製品は、実はCISPRがまとめた「ルール」に沿って設計されていることが多いです。この規格を「CISPR規格」と呼びます。たとえば、
- CISPR 11:医療用や工業用機器の妨害電波についてのルール。
- CISPR 25:車や自動車に関する電磁波のルール。
- CISPR 22:パソコンやIT機器から出る電波について。
これらの規格に従わないと、その製品が市場に出せないこともあります。だからこそ、メーカーはこのルールを守りながら製品を作る必要があります。
CISPR適合マークは?
CISPR自体にはCEマークのような「認証マーク」は存在しません。ただし、CISPR規格に基づく試験をクリアした製品は、各国の法規制や地域規格(例えば、EUでのCEマーキングの要件など)に適合することが可能になります。
たとえば、EUではCISPR規格がEN規格に統合されており、EN 550xxシリーズ(CISPR規格の番号に対応した形式)として採用されています。これに適合することがCEマーク取得の条件の一部となることがあります。同じように、CISPR規格は他の地域の規制(例えば、FCC規格やVCCI)にも影響を与えています。
したがって、CISPRそのもののマークはありませんが、それに基づいた試験をクリアすることが、CEマークなど各種規格認証を取得するための重要なステップとなっています。
まとめ
CISPRというと普段は意識することがないかもしれませんが、実は私たちの生活の裏側で、いろいろな電化製品が「ケンカ」しないように守ってくれている存在なのです。今後、電子機器がますます増えていく世の中で、CISPRの役割はさらに大切になっていくことでしょう。
次に電化製品を買うとき、「この製品もCISPRの基準を守ってるんだなー」なんて、ちょっとだけ思い出してみてください。それだけでも、ちょっと身近に感じられるかもしれませんね。