電子負荷装置は何らかの電源につないで初めて用を成します。しかし、この「つなぐ」事には意外に関心が払われていないことが多く、そのため電子負荷装置の性能を上手く使えていない場合があります。
電流を導体に流すと、流す量とその経路の抵抗に比例した電圧が両端で降下します。これはオームの法則として誰もが知っているところです。しかし、電子負荷装置を使用する際、装置と電源の間の配線抵抗がどの位あり、具体的にどの程度電圧が下がるのか、といったことは知らないで使用されている事が多いのでは無いでしょうか?
配線経路上での抵抗は、主に
- 配線線材自身の抵抗
- 端子台などでの接触抵抗
の2つで構成されます。
線材自身の抵抗はどの程度でしょうか?例えば、線材の径がAWG(American Wire Gauge)で言うところ12AWG(直径約1mm)の線材であれば、その直流抵抗は長さ1mあたり0.005Ω(5mΩ)程度となります。直流抵抗はほぼその線材の断面積に反比例しますので、おおよそ断面積がAWG12の半分のAWG15であれば直流抵抗は倍の1mあたり0.01Ωにも達します。
これに対し、接触抵抗は多くの場合一桁以上高い抵抗値になります。例えば、多くの端子台は仕様上で数十mΩ(以下)の接触抵抗を明記しています。更に、圧着端子などを使えば端子と線材間でも接触抵抗が発生します。
もし、15AWGの線材1mを両端圧着端子を用いて端子台に繋ぐ方法で配線した場合には、合計で最悪数十mΩ~100mΩ近い配線上の抵抗が電子負荷装置と電源の間に挿入される事になります。この様な大きな抵抗ですと、10Aも電流を流すと0.数V~1V近い電圧降下が発生する事になります。
しかし、電源の出力電圧は電源の出力端で測るし、電子負荷装置の端子でたとえ1V程度降下してもたいして問題無いのでは?と思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
例えば、フの字垂下形式の過電流保護回路の動作試験などを行う場合、負荷電流を上げていくに従い出力電圧が下がります。電子負荷装置の端子での電位差は、保護による出力電圧の低下に電圧降下分の低下が重なって更に小さくなります(もちろん出力電流も制限されるため電圧降下も小さくなりますが)。問題は、電子負荷装置の引ける電流は負荷装置の端子間の電位差に依存すると言うことです。
低くなった端子間の電位差に対し、十分な電流を引く事ができない場合は均衡点で停止し引ききる事ができないか、当社の電子負荷の様に限りなく0V付近まで電圧に比例した電流を引く事ができないタイプの装置の場合は、一定以下に電圧が下がった時点で負荷が開放(OFF)される事になります。負荷が無くなると電源は出力を復帰しますが、端子間電圧が戻った時点でまた負荷が印加(ON)される事になります。あとはこれを延々繰り返し、いわゆるハンチング状態になります。
この様に、限界付近で使用する場合は僅かな配線経路の抵抗も問題になる場合があります。十分に電子負荷装置の性能を使い切るには、配線経路の抵抗も気にしたいものです。
今回は直流抵抗についての話でしたが、負荷電流が時間と共に変化する場合はまた別の事を気にしなくてはなりません。
電流は、直流的な捕らえ方では導体の中を一様に流れますので、その抵抗値が断面積に反比例する事は前回お話した通りです。しかし交流の場合、電流はその周波数が高くなればなるほど導体表面に電流が集中する現象が発生します。この現象を「表皮効果」と呼びます。
太い単芯のケーブルや銅板で配線してあるから十分配線抵抗は小さくなるはずと思っていたら、実はその一部分しか電流経路として使用されず、実質断面積が小さくなり、想定より抵抗(交流抵抗)が高くなると言うことが発生します。
表皮効果の程度は、電流の流れる深さ「表皮深さ」で表します。この深さが薄い程表皮効果が大きいと言うことになります。では、例えば一般的な銅線に働く表皮効果はどの程度のものでしょうか?
「表皮深さ」はその導体の電気抵抗の2倍の2乗根に比例し、導体の絶対透磁率と電流の角速度(角周波数)の積の2乗根に反比例します。
一般的な銅線の場合の電気抵抗と絶対透磁率の設定にも因りますが、一般に使用される銅の電気抵抗(導電率)58E6[S/m]と、透磁率4πE-7[H/m]を使用して計算すると、周波数が50/60Hzで10mm弱、1KHzで2mm強、1MHzにいたっては66μmと、本当にごく表面にしか電流が流れないことが解ります。高速に負荷電流を引くためには、この表皮効果をいかに抑えるかが非常に重要な問題になることが直感的にお解かり頂けると思います。
実は表皮効果は古くから知られており、対策として太い単芯線を使うのではなく、絶縁された細い複数の線をより合わせた線を使うことが行われてきました。その代表格がリッツ線(Lits wire)です。中波ラジオのバーアンテナに巻かれていたコイルなどにも使われているので、ご覧になったことのある方も多いかもしれません。
下の図が単芯線とリッツ線の構造を単純に表した図になります。リッツ線は、単芯線と断面積は同じでも表面積を増やすために線を分割した構造になっています。これにより、電流が実際に流れる断面積を稼ぎ、抵抗(交流抵抗)を下げるようになっています。
当社では、電子負荷装置用にリッツ線を0.5m~2mまで両端を処理した形で、Low-Lケーブルの名称で販売もしております。是非お問い合わせ下さい。
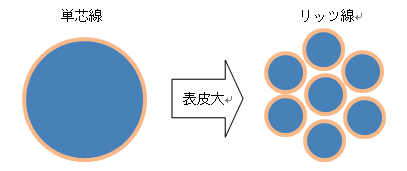
2本の線をツイストして1つに束ねた線 – ツイストペア線には、ただの平行線(バラ線)と比較して
- ノイズに強い(ノイズを出さない、受けない)
- インダクタンスが小さくなる
と言う2つの利点があります。ここでは、電子負荷を使う場合に重要な要素となるインダクタンスが小さくなる理由について見ていきます。
ご存知の通り、導体中を電流をが流れるとその進行方向に向かって右回りに磁界が発生します。これは右ねじの法則として知られているものですが、電子負荷装置と電源を繋ぐ線ではどの様な磁界が発生しているのでしょうか?
電流は行きと帰りの線で反対方向に向かって流れることになりますので、磁界が線を中心として反対回りに発生することになります。平行線の場合、ある点を切り取って見れば、中心部では打ち消しあいますが全体としてはを2本の線を囲むような磁界になります。
平行線全体としては、電流の流れに沿って渦巻き状に連続的に発生する磁界が合成された結果、斜めに同じ向きに磁束が走ることになります。同じ方向に走る磁束は互いに加算されますので、結果的に平行線で発生する磁界は強められることになります。
これに対して、ツイストペア線において一対のペアに着目すれば、これは平行線となんら変わりありませんので同じ状態になります。しかし隣接するペア同士を比べると、1本1本の磁界の方向が逆になりますので当然合成磁界の向きも反対になります。つまり、交互に逆向きに磁界が発生しますので、隣接するペア同士では互いに磁界が打ち消しあうことになります。
インダクタンスは誘導起電力の誘導係数ですが、誘導起電力は単位時間当たりの磁束の変化が大きいほど大きくなりますので、磁束を強める方向に働く平行線より、弱めるツイストペア線の方がインダクタンスは低いと言うことになります。
過渡応答を測定する場合などはもちろん、少しでもインダクタンスを小さくした方が良い場合は必ず電子負荷と電源はツイストペア線で繋ぎましょう。
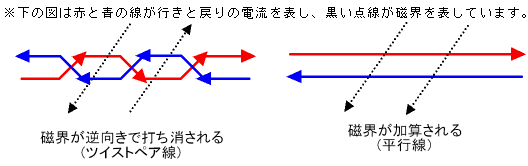
下の図1は、電子負荷装置に繋げた場合の負荷電流ループに寄生するインダクタンスを現した等価回路になります。V2が試験対象の電源、R4とL5は電源自身に含まれる抵抗とインダクタンスになります。L3とL4は電子負荷と電源の間を繋ぐ配線の持つインダクタンスであり、L1とL2が電子負荷装置自身のインダクタンスになります。
計測器や電子負荷装置を使って電源の評価や実験を行う時にはついつい、その計測器や電子負荷装置の存在を無視して(影響を与えないものとして)、その結果を評価しがちになりますが電子負荷装置を回路に加える以上その影響はは免れません。
例えば数mオームのインピーダンスが問題になる燃料電池のインピーダンスを測定しているつもりが実は電子負荷自身のインダクタンスが大きく、それを加えた回路として測ってしまい、何を測っているのか解らない様な結果になってしまうことも考えられます。
こういった用途には十分に内部インダクタンスの低い電子負荷装置を使用する必要があります。ただ電子負荷装置の内部インダクタンスを公表しているメーカーは多くありません。
ちなみに当社では電子負荷装置の内部インダクタンスを公表しています。下の一覧表を見ていただければ解るとおり、スルーレートの早い高速機で20nH~80nH、汎用機(ELA-305)でも250nHと非常に小さな値となっていますので回路全体に与える影響は非常に小さくなっています。
どの様な計測器や電子負荷装置を使っても、計測をすると言うことはその対象に対して何らかの干渉を加える事になります。電子負荷装置も含め計測器の選択には気をつけたいものです。
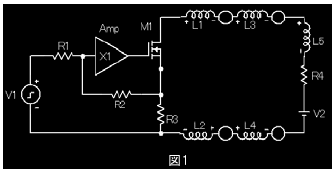

電子負荷装置特有の誤差と言えば、当然ながら設定した負荷に対する実際の負荷との差異のことを指します。一般にこの差異の程度を負荷設定の確からしさと言うことから、「負荷設定確度」又は単に「設定確度」と呼ばれる指標で表します。
「設定確度」の表し方は各メーカーにより異なります。例えば、当社であれば以下のように表しています。
±0.2% of stg. ±15mA ELL-355(定電流モード – 15Aレンジ)
±0.5% of Conv. Curr. ±0.2% of f.s. ELL-355(定抵抗モード – 全レンジ)
これは、設定値の0.2%分の誤差と最大15mAの固定誤差の合計分、設定値がずれる可能性があることを表しています。例えば定電流モードで1Aを設定すると、最悪の場合以下のように17mAの誤差が発生する可能性があると言うことを表しています。
1A × 0.002 + 0.015 = 0.017 (17mA)
では、同じ負荷を負荷モードを変えて設定すると結果は同じになるのでしょうか?
定抵抗モードで電源電圧5Vの時に、やはり1Aの電流を期待して5Ωを設定したとするとどうでしょうか?
(5V ÷ 5Ω) × 0.005 + 15A(15Aレンジの場合) × 0.2% = 0.005 + 0.030 = 0.035 (35mA)
となり、同じ1Aの負荷であっても、モードにより最終的な確度が倍も異なることが解ります。
定抵抗負荷モードは、定電流モードと比較すると負荷電流制御に加えて外部の電圧をセンスし、これを制御系に加える事が必要になる都合上、誤差要因がどうしても増えることになってしまい、設定確度が定電流モードに比較して出にくいと言う性質を持っています。
このように「設定確度」は負荷モードによっても異なります。漠然と同じ負荷量だからどのモードでも構わない、と言う訳には行きません。目的に沿った最適な負荷モードを選択し、最良の条件でご利用下さい。
